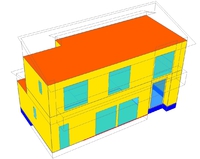2011年06月25日
静岡県文化財建造物監理士
昨年から県教育委員会が始めた、「文化財建造物監理士」養成講座、
残念ながら、去年は応募者多数だったので、抽選となり受講できなかった。
今年度の募集が始まるとすぐに応募し、めでたく今年は受講できることに。
この監理士は県教育委員会が認める資格で、地域の文化財を保護することができる専門家として登録される。
ただ、その講習内容はかなりハードで、机の前に座って学のは、第1回目と最終回だけ、それ以外はすべて屋外の実地研修になる。
その屋外実地研修の必需品がこれ。
 三角スケール、さし金、コンベックス。
三角スケール、さし金、コンベックス。
普通、目盛は㎝単位だが、これらは全て、単位が尺です。
ただ、これらの尺目盛の測定器具、実は計量法という法律で禁止されていている(罰金まである)「ご禁制の品」なのです。
(尺相当目盛付などと書かれて販売されている)
当然JIS非認定品です(と言っても精度が低い訳ではない)
メートル単位が使われる前に建造された建物は尺目盛でないと計測できないのです。
現在の建築の世界でも、木造住宅の分野では尺の単位は生きています。特に大工さんとの会話は尺ですると早い。尺の単位の一つ「間」(1間=6尺≒1.82m)は畳の長さであり、それは日本人の計測感覚の指標となっています。
でも最近は畳のない家に育った若者もいて、この感覚が伝わらないことも・・・。建築を業とする我々にとって、危機的状況なのではと思います。それとも、時代が変わってきたのでメートルでものが考えられる世代が育ったのか?
残念ながら、去年は応募者多数だったので、抽選となり受講できなかった。
今年度の募集が始まるとすぐに応募し、めでたく今年は受講できることに。
この監理士は県教育委員会が認める資格で、地域の文化財を保護することができる専門家として登録される。
ただ、その講習内容はかなりハードで、机の前に座って学のは、第1回目と最終回だけ、それ以外はすべて屋外の実地研修になる。
その屋外実地研修の必需品がこれ。
普通、目盛は㎝単位だが、これらは全て、単位が尺です。
ただ、これらの尺目盛の測定器具、実は計量法という法律で禁止されていている(罰金まである)「ご禁制の品」なのです。
(尺相当目盛付などと書かれて販売されている)
当然JIS非認定品です(と言っても精度が低い訳ではない)
メートル単位が使われる前に建造された建物は尺目盛でないと計測できないのです。
現在の建築の世界でも、木造住宅の分野では尺の単位は生きています。特に大工さんとの会話は尺ですると早い。尺の単位の一つ「間」(1間=6尺≒1.82m)は畳の長さであり、それは日本人の計測感覚の指標となっています。
でも最近は畳のない家に育った若者もいて、この感覚が伝わらないことも・・・。建築を業とする我々にとって、危機的状況なのではと思います。それとも、時代が変わってきたのでメートルでものが考えられる世代が育ったのか?
Posted by kura-ft at 07:12│Comments(0)
│文化財